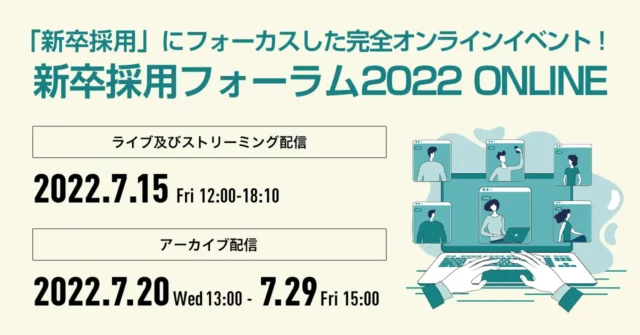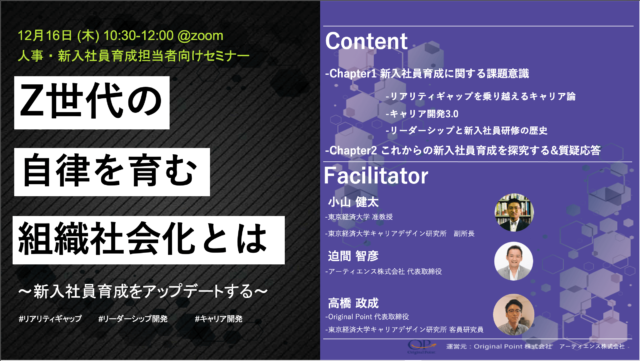大学キャリア教育 事例
関西大学 企業連携型プログラム”キャリスタ”のメンター制度の価値とは?
コクヨ、ロッテ、ワコールをはじめ業界をリードする企業と連携して行うP B Lプログラム「キャリスタ」。関西大学が展開するこの実践的な課題解決型プログラムでは、過去の参加学生がメンターとして後輩をサポートする独自の仕組みを取り入れています。プレイヤーからメンターへと役割を変えることで、学生たちはどのような学びを得ているのでしょうか。今回は、メンター経験者3名に、その価値について伺いました。
メンター経験者(学部・学年は、インタビュー当時)
• 政策創造学部4年 山崎鈴果さん(大手機械メーカー就職)
• 商学部3年 池田奈々美さん(就職活動中)
• 化学生命工学部4年 野坂美希さん(大学院進学)

プレイヤーとメンターの視点の違い ―支援する立場で見えてきた新たな気づき―
Q.まず、メンターに応募したきっかけを教えてください。
野坂さん:1年生の時にキャリスタのプレイヤーとして参加して、その経験を後輩たちにアドバイスできたら良いなと思ったんです。また、複数のチーム活動を客観的に見られる経験ができることも学びが得られる意味で魅力でした。
――最初にプレイヤーとして参加したのは、どんな理由からでしたか?
野坂さん:当時はちょうどコロナ禍で、大学生活が始まったばかりなのにオンラインになってしまって。一般入試で入学したこともあり知り合いが少なく、仲間を増やしたいという気持ちで参加しました。
池田さん:私は2年次生の時に参加者としてキャリスタを経験し、その時のメンターの方々の存在が印象的だったんです。参加者とメンターでは見る視点が全く違うことに気づき、その経験をしてみたいと思いました。
――山崎さんは、どのような思いで応募されたのでしょうか?
山崎さん:私自身、2年次生の時にプレイヤーとして参加した際、チームビルディングがうまくいかなかった経験があります。メンバー間の相互理解が不足していて、なかなか意見が出ない状況でした。その反省から、次は支援する側として関わりたいと考えました。
Q.実際に経験してみて、プレイヤーとメンターの違いをどのように感じましたか?
山崎さん:プレイヤーは思いついたアイデアを形にしていく立場ですが、メンターは答えを見つけるためのヒントを提示する役割です。時には自分が答えを思いついても、直接教えるのではなく、そこに至るためのヒントを出すことが求められます。この経験は、後の就職活動でも評価していただくことが多かったです。
野坂さん:プレイヤーの時は自分のチームの状況しか見えていませんでした。でもメンターになると、複数のチームを見ることで、チームごとの熱量の違いやグループの特徴が見えてくるんです。各チーム特性の把握を通じ、チーム活動の本質を学ぶことに繋がるメンターならではの経験でした。
――具体的にどのような違いが見えてきたのでしょうか?
野坂さん:例えば、あるチームは積極的に意見を出し合えているのに、別のチームは遠慮がちでなかなか本音を言えていないといった違いです。メンターの立場だからこそ、そういった特徴を客観的に捉えることができました。
池田さん:私はメンターの役割を『森を育てるガーデナー』のように感じていました。プレイヤーは0から1を作り上げる立場ですが、メンターは外からマネジメントする立場。チームの成長過程を見守りながら、適切なタイミングで必要なサポートを提供することの難しさと面白さを実感しました。
メンターとしての成長体験 ―チーム支援で得た学びとスキル―
Q.メンター活動を通じて、最も成長を実感した経験や身についたスキルについて教えてください。

山崎さん:私が最も身についたと感じるのは「アドバイスの仕方」です。最初から否定するのではなく、「まず良いところを認めることから始め、それから考えてほしい方向性に導いていく」といった伝え方は、サポート中、常に考えながら実践していました。その過程で、自分の考えを整理して図式化するなど、効果的に伝えることの重要性も学びましたね。
野坂さん:私は、チームとの関わり方で多くの学びがありました。最初は介入のタイミングに躊躇していたんです。でも、ただ質問を待っているだけでは十分なサポートができない。特に話が詰まっているチームには、自分から積極的に関わっていく必要があると思って、サポートしていきました。でも、メンバー達の自主性も大事にしたいので、適度な距離感は保つ。このバランス感覚は、難しかったけど、徐々に身についていった実感があります。
池田さん:私は塾講師のアルバイト経験があって、個別のアドバイスは得意だったんです。でも、チームビルディングには最初苦労しました。「チーム全体にどう良い影響を与えていくか」という視点でのマネジメントは、メンターだからこそ求められる役割でした。活動を通じて、状況を客観的に見る力や、チームを導いていくマネジメントスキルが身についたと感じています。
Q.メンターとして活動する中で、特に印象に残っているエピソードはありますか?
野坂さん:あるチームのリーダーが泣きながら相談に来たことが強く印象に残っています。チームビルディングがうまくいかず、リーダーとしての役割に悩んでいたんです。その時、自分自身もメンターとして、もっと早くチームの状況を把握できていれば良かったと反省しました。
――その経験から学んだことはありますか?
野坂さん:はい。チームのアウトプットの質を高めることも大切ですが、その前提となるチームの土台づくりがより重要だと気づきました。メンターとして、どのタイミングで、どのように介入するべきか。その判断の難しさも実感しています。

池田さん:私の場合は、担当していたチームが優勝したことが大きな思い出です。最初から最後まで一貫して見守ってきたチームだったので、その成長過程を間近で感じられました。メンバー一人ひとりが徐々に本音を話せるようになり、チームの雰囲気が変わっていく様子を見られたことは、貴重な経験でした。
メンター経験がもたらした未来への影響 ―就職活動とこれからのキャリアデザイン―
Q.メンター経験は、就職活動や将来のキャリアデザインにも影響を与えたそうですね。
山崎さん:就職活動では、この経験が大きな強みになりました。特に、人の話をよく聴き、適切なタイミングで必要なサポートを提供するという姿勢は、面接でも評価していただけました。将来は人事部門で、社員の方々の働き方をより良くする仕事に携わりたいと考えています。
――その思いは、メンター経験から生まれたものなのでしょうか?
山崎さん:そうですね。メンターとして、チームの課題に向き合う中で、『働く人の環境をより良くしたい』という想いが芽生えました。最初の配属先で現場を経験した後は、人事部門で組織の課題解決に関わっていきたいと考えています。
野坂さん:私は大学院への進学を決めましたが、その判断にもメンター経験が影響しています。研究活動も一人ではなく、チームでプロジェクトを進めていくものです。メンターを通じて学んだチームビルディングの経験は、研究室での活動にも必ず活きてくると思っています。
――池田さんは就職活動中とのことですが、どのような影響を感じていますか?
池田さん:社会人の方々と接する中で、プレゼンテーション力や人を惹きつける力の高さに感銘を受けました。そういった実際の姿を間近で見られたことで、自分も成長したいという意欲が高まりました。また、就職先を選ぶ際も、単なる事業内容だけでなく、働く環境や人との関わり方を重視するようになりました。
循環型成長の仕組み ―キャリスタが育む“支援”と“成長”の好循環―
Q.最後に、改めてメンターを経験することの意義について教えてください。

野坂さん:メンターの経験は、自分を成長させるとても貴重な機会です。特に、物事を広く見る力、一歩引いて客観的に状況を判断する力は、学生のうちになかなか得られない経験だと思います。
山崎さん:確かに大変なこともありますが、その分だけ得られるものも大きいです。企業の方々との関わりも含めて、視野が大きく広がる経験となりました。
池田さん:私も2年間メンターを経験して、毎回新しい発見がありました。チームのサポート役として関わることで、自分では気づかなかった自身の特徴も見えてきます。応募を迷っている人には、挑戦する価値のある経験だと伝えたいです。
“キャリスタ”担当 関西大学キャリアセンター山口様より
大学1~2年次にプレイヤーとして経験したキャリスタに、もう1度メンターとしてサポート側で参加できるという経験を大切にして欲しいです。今回の3名のインタビューを聞いていて、メンターとしての活動を通じて掴み取った経験の質の高さに驚きました。社会人になってから経験できるような組織マネジメントに関する学びを既に大学生の就職活動前に得られたこの経験は、就職活動だけでなく、社会人になってからの自身のキャリアデザインという面でも非常に貴重だと考えています。また、参加学生にとって、直近、キャリスタに参加した先輩からのアドバイスは非常に受け入れやすく、プログラムの重要な仕組みとして、今後も継続させていきたいです。
“キャリスタ”プログラム担当 Original Point(株)高橋より
キャリスタのメンター制度は、単なるチームサポートの仕組みを超えて、メンター自身の成長の場としても機能しています。客観的な視点でチームを観察する力、適切なタイミングで介入する判断力、そして相手に寄り添いながらヒントを提供するコミュニケーション力。これらのスキルは、就職活動や将来のキャリアにおいても、大きな財産となっているようです。
また、社会人の方々と近い距離で関わる経験は、「働く」ことへの具体的なイメージ形成にも役立っています。参加学生がプレイヤーからメンターへと役割を変えながら成長していく。この循環が、キャリスタの大きな特徴であり、魅力となっています。
Original Pointでは今後も、このメンター制度を通じて、関西大学の学生の主体的な成長を支援していく予定です。自己成長の機会を求める学生たちにとって、メンター制度は新たな可能性を開く扉となるかもしれません。
Mizuki Muraoka
村岡 瑞妃
大学卒業後、1年間東京都の小学校教員として担任を務める。その後、エン・ジャパン(株)に転職し企業の採用支援や評価・教育研修サービスの提案営業を行う。現在は、Original Pointへ参画し、大学キャリア教育や新卒採用領域の事業推進に携わっている。





 探究レポート
探究レポート
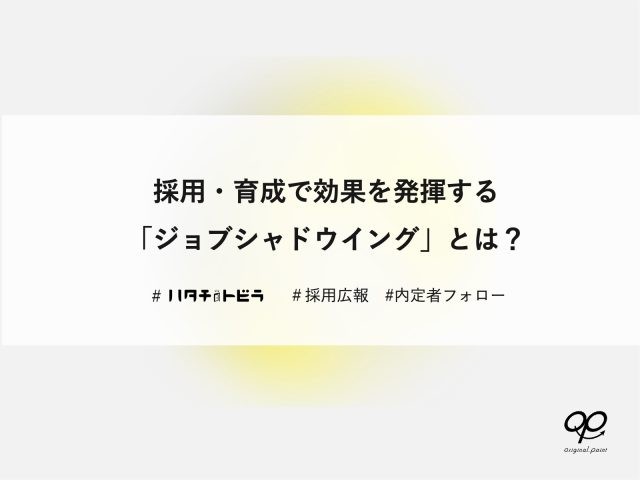
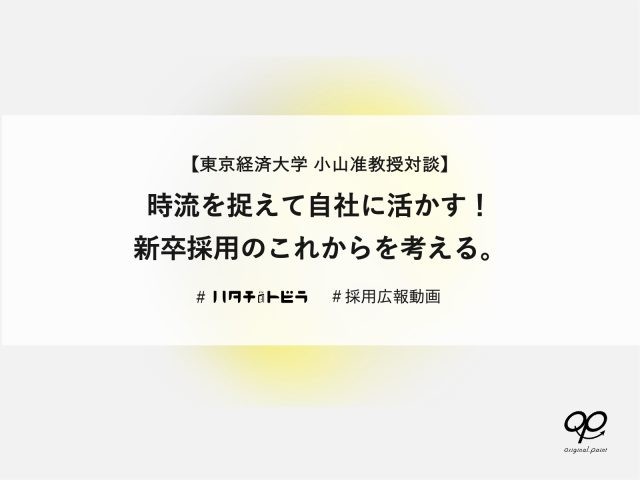
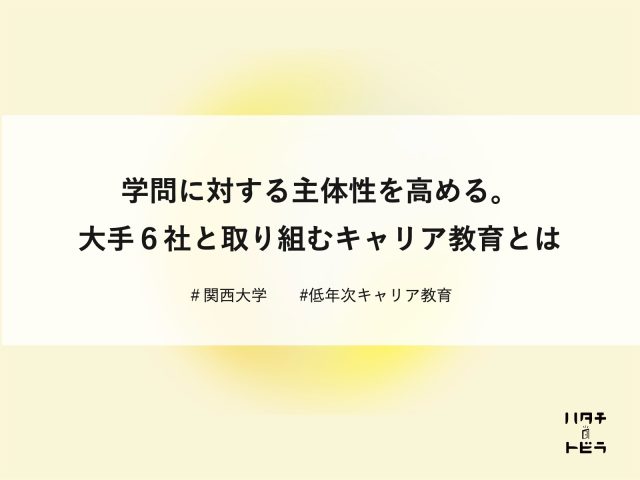
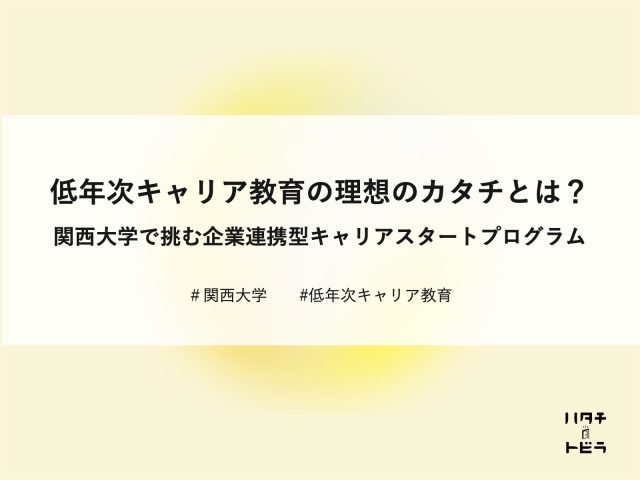
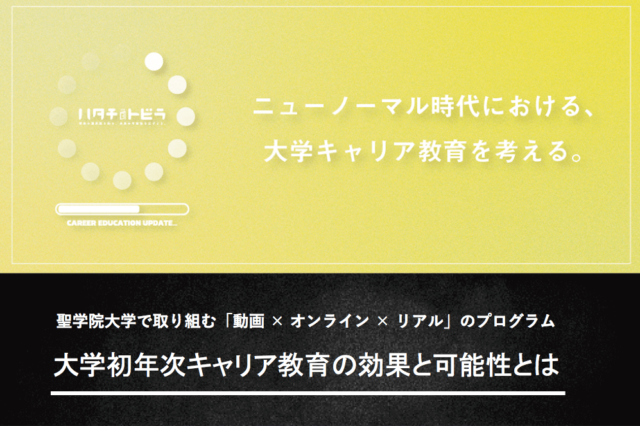
 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 セミナー情報
セミナー情報